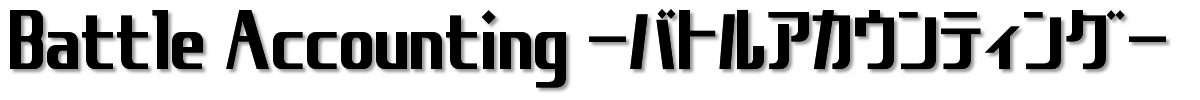日本公認会計士協会(JICPA,関根愛子会長)は5月29日,「2019年版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」を公表しています。
これは,JICPAから委託を受けた監査人・監査報酬問題研究会が取りまとめたもので,2017年4月期決算から2018年3月期(2017年度)決算に係る監査報酬・監査人の実態に関する調査・分析を実施したものになっています。
結論としては、監査報酬については,2013年度から引き続いて増加傾向にあることが示されています。
理由についてはいろいろと考えられると思いますが、ひとつ面白い仮説が。
「監査証明業務の重要性を以前よりも高く認識している企業が増え,それらの企業がより高額の報酬を支払っていることを示唆しているのかもしれない」
実際にこういう傾向があるのかは何とも言えませんが、
不正撲滅への一つの手立てとして監査を利用しようというインセンティブがあるなら、それは素晴らしいことかと思いますね。
個人的には、今後監査は、不正の撲滅を含めた制度に変化していってほしいと思っています。
問題は、監査を受ける企業が、監査を”これならカネを払う価値がある”と思われるようなサービスとして評価してくれるかどうかでしょうか。
最近、あらためて、そうなるためにはどうしたらいいのかということを考えたりしています。
ところで、同報告書の最後に、”監査人の選任と監査報酬のあり方”として、さらに興味深い考察が記載されていましたので、引用します。
金商法では、証券市場に対して重要な虚偽表示のない財務諸表が、無限定適正監査報告書とともに提供されることが前提であり、それが資本市場の安全性や流動性を確保することに繋がり、もって投資者の保護を可能としている。したがって、結果として、経営者と監査人は協働で瑕疵のない財務諸表を市場に提供する義務を負っており、財務諸表に欠陥を発見した監査人は、経営者に対して財務諸表の修正を指導し、経営者に受け入れさせ、財務諸表に瑕疵をなくした上で無限定適正意見とともに市場に供することが期待される。換言すれば、監査人は、財務諸表の欠陥を発見し、財務諸表の修正指導をすることなく、監査報告書で除外事項として指摘するだけでは、市場の期待ないしは金商法の期待を果たしたことにはならないのであり、そのような事態はあくまでも例外的な事態と捉えられる。
果たして監査人と経営者との間の信頼を醸成できないような外部の第三者ないしは国家が強制的に選任し割り当てた監査人は、むしろ財務諸表や内部統制の粗捜しに徹し、その成果を披瀝することに熱心となるおそれすらある。経営者の側からすれば、そのような監査人と自社の秘密に属するような事項を共有しようとは思わないであろうし、敵対的な関係が生じる可能性もある。この結果、資本市場には、瑕疵のある財務諸表と除外事項付きの監査報告書が提供されるが、当該情況が常態化した市場では取引の円滑性も安全性も投資者に対して保障できないであろう。
経営者が監査人を信頼するからこそ、秘密を共有し、正しい決算書が作成されるようになるというロジックですね。
今の制度を支える考え方だと思います。
これは確かにそのとおりな部分はあるのだと思います。
しかし、何でもそうですが、物事は正しく疑う(懐疑心を持つ)というのは必要です。
そこで敢えてこのロジックを疑ってみると、以下のような私見(気付き・疑問)を得ました。
まず、「監査人は財務諸表や内部統制の粗捜しに徹し、その成果を披瀝することに熱心になるおそれ」とありますが、今の制度であっても、ある程度はこれが既に顕在化していませんでしょうか。
というか、監査人はあら捜ししなければ、虚偽表示など見つけられないのではないかと思います。虚偽表示が見つけられないことが、最もおそれるべき事態です。
この”熱心になるおそれ”が試査を前提として、効率的に監査を実施することがなくなってしまうことを危惧する意味だとしても、時代はビッグデータを用いた効率的精査へ移行していまして、リスクのあるところはとことんあら捜しすることになります。
経営者の不正リスクが感知される領域については、この傾向が更に強まるでしょう。
クライアントは、もうすでに”十分にあら捜し”と感じていることも多いのではないでしょうか。
また同様に、敵対的な関係は、一部の監査現場では既に発生しています。
監査人と被監査会社の間には、どうしても超えられない壁があります。
私の経験的には、多くは(一部の)監査人側のサービス精神の欠如、藪蛇リスク、過去の監査判断に関する手のひら返し等、監査人側の限界がこの状況を作り出していると分析していますので、
これが公的機関になろうが、そうでなかろうが、そんなに変わらないんじゃないかなあと思う次第です。緊張感はあったほうがいいと思うので、それ自体は否定しません。
でも、敵対的にならないようにするための工夫は存在していて、実際に敵対的になっていない現場も多数あります。
そのようなベストプラクティスを共有することのほうが重要なのかもしれませんね。