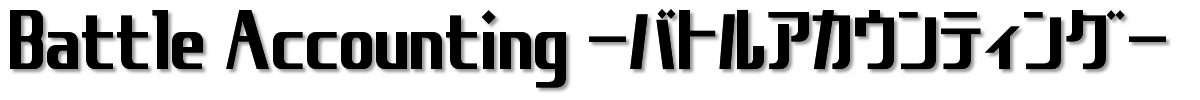Contents
【減損会計】キャッシュ・フローについて理解を深めるためのポイント
減損会計においては、将来キャッシュ・フローについて見積ることが要求されているわけですが、この見積りには多くのルールがあります。
今回は、これについて触れていきます。
使用価値
使用価値(value in use)は、資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フロー(CF)の現在価値です(減損会計基準 注解(注1)4. 参照)。
ポイントは、以下です。
(2)割引現在価値であること
認識と測定
減損会計において、将来キャッシュ・フローについて定められている場面は、大きく2つであることを確認しましょう。
▶割引前キャッシュ・フローを見積もる場合
▶使用価値を見積もる場合
この2つがゴッチャになりがちですので、意識してみていきましょう。
期間
キャッシュ・フローを見積る期間
適用指針37.(1)(2)によれば、以下の通りです。
| 認識 | 測定(使用価値) | |
|---|---|---|
| 期間 | 経済的残存使用年数と20年のいずれか短い方(*1) | 経済的残存使用年数(*2) |
ポイントは、認識では20年を上限とするが、測定では使用価値(割引現在価値)を計算する必要があるため、そのような制限は不要である点です(正確な計算のためにはむしろ不要)。
(*1) 認識の場面で、20年という制限があるのは、以下の理由によります。
⑴少なくとも土地については使用期間が無限になりうることから、その見積期間を制限する必要があること
⑵一般に、長期間にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性が高くなること
(2) 期間を考えるときには、いま、認識と測定のどちらの話をしているのか意識する
主要な資産
22.資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産である主要な資産(減損会計基準 注解(注3)参照)は、資産のグルーピングを行う際に決定され、当期に主要な資産とされた資産は、原則として、翌期以降の会計期間においても当該資産グループの主要な資産となる(第101項参照)。
23.企業は、主要な資産を決定するにあたって、以下のような要素も含めて総合的に判断する(第102項参照)。
⑴ 企業は、当該資産を必要とせずに資産グループの他の構成資産を取得するかどうか。
⑵ 企業は、当該資産を物理的及び経済的に容易に取り替えないかどうか。
なお、土地等の非償却資産や建物等の経済的残存使用年数が20年を超える資産を主要な資産とする場合にも、当該資産が資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるかどうかに留意する必要がある(第103項参照)102.一般に、企業は、当該資産を必要とせずに資産グループの他の構成資産を取得するか、当該資産を物理的及び経済的に容易に取り替えないかなどを考慮して、主要な資産は決定されると考えられるが、資産グループの他の構成資産と比較して、当該資産の経済的残存使用年数の長さや取得原価及び帳簿価額の大きさなども勘案される場合があると考えられる。企業は、これらの要素を考慮して、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産である主要な資産を、総合的に判断する(第23項参照)。
なお、資産グループの主要な資産を決定するにあたり、個々の資産ではなく、経済的残存使用年数は異なるが物質的性質や用途等において共通性を有する複数の償却資産の集合体が、最も適当であると判断される場合がある。そのような場合には、当該集合体を資産グループの主要な資産とし、複数の償却資産の経済的残存使用年数を平均した年数を当該主要な資産の経済的残存使用年数とすることができる。103.我が国における土地等の比重に鑑みると、前項で示したような要素を考慮すれば、実務上、賃貸ビルや倉庫などに限らず、土地等を幅広く主要な資産と判断するケースが想定される。土地等の非償却資産や建物等の経済的残存使用年数が20年を超える資産を主要な資産とする場合にも、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるかどうかに留意する必要がある(第23項なお書き参照)。
主要な資産の決定は、キャッシュ・フローの期間の決定にとって非常に重要です。というか、期間は主要な資産が何であるかという判断によります。
したがって、主要な資産の判断については、上記のような多くのガイダンスが用意されています。
主要な資産を検討する場合に留意すべきポイントは、以下です。
- 土地などの残存年数20年を超えるような期間の長いものを主要な資産とできるかどうか
- 共通性を有する複数の償却資産の集合体を主要な資産とできるかどうか
のれんがある場合
24.共用資産やのれんは、原則として、主要な資産には該当しない(第104項参照)。
原則
共用資産は、本社資産のイメージですね。
のれんは、多くの場合、企業結合で生じる計算上の差額に過ぎないものです。
これらは、104項にも記載があるように一般的にキャッシュ・フローを生成する直接の理由にはなりません(もちろん、例外はあるとは思いますが)。
そのため原則としてこれらは主要な資産にならないとされています。
例外
しかし、例外はあります。
104項によると、それは例えば以下のような場合です。
共用資産:
ある特許権が複数の資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与するため共用資産に該当し、当該特許権がいずれの資産グループにおいても、それぞれの資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるような場合のれん:
固定資産をほとんど含まない営業の譲受から生じた営業権が、当該資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるような場合
さらに、119項にも例外としての記載があります。
つまり、共用資産やのれんに減損の兆候があるような場合です。
この場合は、より大きな単位でグルーピングを行うこととなりますが、共用資産やのれんを基準にして見積期間を考えることになります。
なお、のれんについては、ぜひ以下の記事をご覧ください。
見積方法
減価償却費
キャッシュ・フローにおける減価償却費の取り扱いについては、キャッシュを算定するんだから、利益に足し戻すんでしょうと思ってしまいます。
確かにそれが理論的なのですが、減損会計においては、(やはりここでも)場面をわけて理解をする必要があります。それは、以下のような場面です。
2.認識/測定
順にみていきます。
兆候
減損の兆候の判定要件の一つに、以下のようなものがあります。
12.資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合には、減損の兆候となる(減損会計基準 二 1. ①参照)。
つまりは、事業の損益またはキャッシュ・フローの過年度推移をとってみて、それが継続して赤字になっているような場合は、「減損必要かもしれない」となるわけです。
この指標については、「損益」と「キャッシュ・フロー」の2つが提示されています。
しかし、減価償却費は非現金支出費用ですから、会計上の費用です。なので「損益」計算上は利益から控除され、「キャッシュ・フロー」からは控除されません。
ここで、基準は「損益」の使用を念頭においていると考えられます。
80.単年度の財務情報を基礎にして減損の兆候があるかどうかを判断するためには、企業が生み出す将来のキャッシュ・フロー予測において、現金基準に基づく利益よりも発生基準に基づく利益が有用と考えられていることと同様に、通常、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」ではなく、「営業活動から生ずる損益」が適切であると考えられる。また、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」については、その把握が、管理会計上も「営業活動から生ずる損益」の把握と比べ一般的ではない。このため、(略)両方から減損の兆候を把握することとすると、実務上、過度な負担となるおそれがある。
したがって、減損会計基準の定めは、管理会計上、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」だけを把握している企業の場合には、「営業活動から生ずるキャッシュ・フロー」によって減損の兆候を把握することも可能であることを示しているものと解される(第12項⑶参照)。
つまり、仮に「営業活動による損益」と「営業活動によるCF」の両方を把握している場合でも、単年度の財務情報を基礎にして兆候を判断する場合には、損益を使用することが適切ではないかという感触を読みとれます、
そもそも、管理会計上「営業活動によるCF」だけしか把握していない企業は多くないのではないでしょうか。
結局、現金主義による業績把握をしてしまうと、特に投資額が何年かに一回という場合には判定に重大な影響を与えますよね。5年に一回大きな更新投資をしているような会社であれば、4年間の業績は妙に良くなってしまいます。
そのため、投資額が償却費としてならし計算された利益のほうが適切な判断ができるのです。
●その場合、減価償却費は控除する(適用指針12項(1))
認識・測定
兆候の時と違って、認識と測定の場面では、「キャッシュ・フロー」を計算することになります。
そのため、損益計算ではないので、非現金支出費用である減価償却費は、控除しません。
兆候の場面とは、取り扱いが異なるところです。
本社費
以下のように、本社費については、兆候・認識・測定のいずれのケースにおいても控除することになります。
固定資産の減損に係る会計基準(企業会計審議会)
(4) 将来キャッシュ・フロー
⑤ 資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローを見積るためには、当該資産又は資産グループが将来キャッシュ・フローを生み出すために必要な本社費等の間接的な支出も考慮する必要がある。したがって、資産又は資産グループに関連して間接的に生ずる支出は、関連する資産又は資産グループに合理的な方法により配分し、当該資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに際し控除することとした。
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
12.資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合には、減損の兆候となる(減損会計基準 二 1. ①参照)。
⑴ 「営業活動から生ずる損益」は、営業上の取引に関連して生ずる損益であり、これには、当該資産又は資産グループの減価償却費や本社費等の間接的に生ずる費用が含まれ(略)
ところで、本社費用は配賦計算により各資産グループに帰属させることが考えられますが、この配賦計算については恣意性に注意が必要です。以下のような不正事例があるためです。
税金
税金(法人所得税)については、兆候の段階では考慮しませんし、認識・測定の段階でも法人税等の支払額及び還付額を含めない=考慮しない(減損会計基準 二 4.⑸参照)とされています。
このことは、キャッシュ・フローが税引前(法人所得税を考慮しない)であるから、割引率も税引前を使用して平仄を取る、といった論点に繋がっていきます。
更新投資・維持投資
認識・測定において、更新投資・維持投資については以下のように考えます。
資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮し、現在の価値を維持するための合理的な設備投資に関連する将来キャッシュ・フローは、見積りに含める(減損会計意見書 四 2. ⑷②参照)
ということは、不利な計算になります。
しかし、あくまで合理的な計算をしていますので、仕方ありません。
減損からは少し離れますが、例えばDCFで価値計算をする際も、キャッシュ・フローをFCFで算定する場合、CAPEXは需要な考慮事項ですので、そことも整合しています。
割引率
割引率の論点は、測定の側面でのみ出現します。
話を始めると長くなるのですが、ポイントは以下です。
- WACCをちゃんと計算できるか
- 税引後ではなく、税引前の割引率を算定すること
- 税引後→税引前への調整計算の方法は、敢えて簡易的な計算ルールにされていること
割引率については、また別の機会に触れたいと思います。